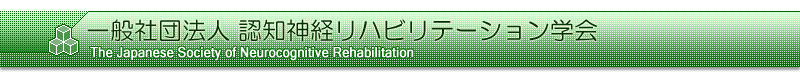Home > 会長からのメッセージ目次 > メッセージNo.134
| ←No.133へ | No.135へ→ |
メッセージNo.134 汝自身を知れ
−ベイトソンの「ここにスイッチがある」という意味
古代ギリシャのアポロン宮殿の入口の壁には、ソクラテスの「汝自身を知れ(know thyself)」という格言が刻まれている。
認知とは「知ること(knowing)」を意味するが、この格言は「自分自身を知れ」という意味である。自己が知ることの対象である。だとすれば、「自己が自己を認知すること」を指している。つまり、「メタ認知」である。
メタ認知とは「自己が知っていることを自己が知る」ということである。確かに、自己を知ることなくして自己を生きることはできない。人間は自己を反省(リフレクション)する。
だが、逆に「汝世界を知れ」と言うこともできる。世界とは環境であり、空間であり、物体であり、他者であり、社会であり、意識であり、心的世界であり、生きてゆく世界のすべてである。世界を知ることなくして世界を生きることはできない。
いずれにしても、自己や世界を知るのは「汝」である。そして、それは「私の身体」を使って「自己や世界を知る」ということでもある。
グレゴリー・ベイトソン(Batoson,G)が、この「汝自身を知れ」について興味深い解釈をしている。それは人間の認知と行為を理解する上で示唆に富む考え方である。彼は『精神と自然』という本で次のように述べている。
私が暗闇で手を伸ばすとする。手が電燈のスイッチに触れる。「おっ、ここにあったかのか」と私は胸の中でつぶやく。「これでワタシはソレをつけることができる。」
だが電燈をつけることが目的なのであれば、何もスイッチの位置と私の手の位置を知っている必要はないのではないか。手とスイッチが接触したことを感覚器官が報告してくれれば、それで十分ではなのか。「ここにあったのか」という私の認識がまったく誤りであったとしても、手はとにかくスイッチに触れていたのだから、電燈をつけることはできたわけだ。
私の手はどこだ? これが問題なのである。自分の手の位置を知るという己を知ることの一項目が、スイッチを捜すこと、スイッチがどこにあるのかを知ることに対して、極めて重要かつ特異な関わり合い方をしている。
例えば、私が催眠術にかかっていて、現実には真っ直ぐ前に伸びている手が、頭上に伸びていると信じ込んでいたとしよう。この場合、私はスイッチが頭の上にあると思ったことだろう。そればかりか、首尾よく電燈がついたことで、スイッチの位置についての考えの正しさを立証したとすら思ったかもしれない。
われわれは自分たちについて様々な見解を外界に投影している。誤った見解をもつことも往々にしてあるようだが、それでもその誤った見解を基盤として、結構うまく動き回ったり、たちふるまったり、友人と相互作用したりしている。
ここまでを読むと、「汝自身を知れ」というのは、自己の身体の位置を空間的に知ることが「自己」を知ることであり、そのことが「スイッチがどこにあるかを知ること」の前提条件だと語っているように思うかもしれない。しかしながら、ベントソンはそんな当然のことを強調しているわけではない。彼は、「ここにあったのか」に「情報」という概念を持ち込み、次のように説明している。
この”自分”というもの、これは一体何なのか? “汝自身を知れ”という、いにしえの忠告に従うことで、いかなる情報が新たに加わるのか?
話を戻そう。手が頭上に、スイッチが肩の高さにあると私が”知って”いるとする。そして、スイッチに関しては正しいが、手の位置に関しては誤っているとする。この場合、いくらスイッチを捜しても、手がスイッチに触れることはあるまい。スイッチの位置をなまじ”知って”いることが禍いしているのだ。”知って”いなければ、ランダムな試行錯誤の繰り返しの中で、手がスイッチに触れることもあるだろうに。
では、自分について知るべきか知るべきでないかの基準は一体どこにあるのか? 誤った見解を持つより、何も知らない方がよいのはどういう場合か?
己を知っていることが実際的見地から必要なのはどういう場合か? こういうことは知らなくても、考えさえしなくても、人の暮らし成り立つもののようである。
もっと謙虚な疑問をもって、問題にアプローチしていこう。そもそもイヌは自己を認識しているのか?
自分について何も知らないイヌが、ウサギを追いかけることは可能だろうか? 「汝自身を知れ」とかまびすしく叫び立てるあの命令の山は、われわれが抱え込んだ「意識」というものが、その数々の矛盾のつぎ当てにせっせと織り紡いでいる、途方もない幻想のもつれにすぎないのだろうか?
ここでイヌとウサギとが、それぞれ独立した別個の生物であるという見方を捨てて、ウサギとイヌの全体を一つのシステムと見よう。すると問いは、こんなふうに形を変える―この部分があの部分を追いかけることが可能であるためには、システム内にどんな情報が存在しなくてはならないのか?
そして追いかけぬわけにはいかなくなるためには?
こう考えると答えもかなり形相を変える。そこで必要とされる情報は「関係」についてのものに限られるのだ。ウサギは逃げることで、イヌに対し、追いかけろというシグナルを出したのかどうか?
電燈の例が参考になる。手(私の手?)がスイッチに触れた時、そこに手とスイッチとの関係についての情報が生じた。そして、その情報さえあれば、電燈をつけることは可能だった。私、私の手、スイッチについての個別情報は一切不要だった。
ベイトソンは、イヌがウサギを追いかけることも、手でスイッチを押して電燈をつけることも「一つのシステム」だと強調している。彼はシステム論者である。つまり、「すべての世界の出来事は要素間の関係性によって生じる」と考えている。そして、システム内の各要素間の「相互作用」によって生まれる「関係性」が「情報(information)」であり、その情報の存在こそが、イヌがウサギを追いかけたり、私が手でスイッチを押して電燈をつけるといった、動物や人間の「行為(action)」に必要だと強調している。
このベイトソン流の「情報」の捉え方は、古典的な「サイバネティクス(機械工学)」における感覚フィードバック情報とは違う。また、人間の営みとして、私が身体を空間的に知ったり、私がスイッチの接触を知ったりするという意味での「認知(知ること)」とも違う。なぜなら、私が手でスイッチを押して電燈をつけることは、「私の手とスイッチの関係」によって生まれる情報に由来しているからである。
また、この身体(手)と物体(スイッチ)の相互作用に根ざした情報は、手だけでも、スイッチだけでも生まれない。手を知るだけでは、スイッチを知るだけでは、私が手でスイッチを押して電燈をつけるのに必要な情報は生まれないということである。その行為に「私、私の手、スイッチについての個別情報は一切不要」なのだ。
この点がとても重要である。つまり、「手とスイッチの関係を情報として知ることで行為は生まれる」のである。
ここで情報について復習しておこう。ベイトソンは「情報とは差異によってつくられた差異」であると定義している。ペルフェッティ(Perfetti)は「脳は物理的な差異を認知的な差異に変換する」と述べている。また、ベイトソンによれば「差異、つまり情報という認識が生まれるためには、二つの実体(現実のもの、あるいはイメージされたもの)が必要である」。さらに、「その二つの間の差異が、その二つの間の相互関係に内在的であることが必要である」。つまり、それぞれ一つ(単独)では、認知過程にとって非実体(非存在)であるということだ。「片手では拍手できない」のと同じように、単独で差異はつくれず不可知である。
そのためベイトソンは「差異は、関係性(関連性=意味)という特性があるゆえに、時間や空間の中に位置づけられるものではない」と断定している。そして、「学習と精神の各部位の組織化のためには、すべての基礎となる“結びつける構造”
が必要である」としている。
さらに、ベイトソンは「比較するためにはその2つの間に差異と類似の関係が生じていなければならない」と言っている。ただし、「差異と類似」の関係は「差異があるが類似もある」とか「類似もあるが差異もある」といった関係である。差異と類似はどちらを先に見るかの視点の問題に過ぎない。差異を知るには類似を知っておく必要があり、類似を知るには差異を知っておく必要がある。
つまり、情報は身体にあるわけではないし、情報は物体にあるわけでもない。情報は身体と物体の相互作用の接点(中間)に生まれる。すなわち、行為は身体と物体の関係性として創発(産出)される。
この場合、関係とは「私の手とスイッチの関係」である。私の手もスイッチもシステムの構成要素に過ぎない。こうした行為を生み出すための空間と接触についての情報が必要である。したがって、身体と物体の相互作用に根ざして、「情報を知ること」ことが、「汝自身を知る」ことだと言えるだろう。
「私の手とスイッチの関係」とは何か。まず、私の手の空間的な位置は上肢の位置覚や運動覚で知覚する。上肢を動かすことで「自己中心座標系」における手の空間的な位置は変化する。しかしながら、手の空間の変化だけではスイッチの位置はわからない。スイッチの位置の知るためには接触の変化が必要である。つまり、連続する壁の接触感からスイッチの接触感への変化がスイッチの位置を「ここだ」と教えてくれる。この瞬間、手の空間の位置(運動覚)とスイッチの位置(接触感)が一致する。
したがって、「私の手とスイッチの関係」とは、上肢の運動覚(空間情報)と手の触覚(接触情報)の関係である。身体(手)の空間性だけでも、環境(スイッチ)の接触性だけでも、関係性(情報)はつくれない。暗闇の中で私が手でスイッチを押して電燈をつけるためには、手の空間性の差異とスイッチの接触性の差異が必要である。つまり、2つの差異から3次元空間におけるスイッチの「ここ」という場所は導かれる。
ベイトソンによれば、情報とは「差異の知らせ」であり、「精神の各部分間の相互作用の引き金は”差異”によって引かれる」としている。しかし、ベイトソンが「情報とは差異によってつくられる差異である」と定義しているように、一つの差異だけでは行為は生まれない。情報の構築は「空間的な差異と接触的な差異によってつくられる一つの差異」だと言える。
これは認知神経リハビリテーションの臨床においてもきわめて重要である。たとえば、片麻痺では手足の運動麻痺や感覚麻痺が発生し、「私」が「自分自身と世界」を知ることができなくなってしまうことがある。それは「私」が「汝自身を知る」ことができない状態を招く。
その場合、片麻痺は「情報の構築」が出来なくなっている状態と解釈しなければならない。そして、その回復は「身体と物体の相互作用の接点(中間)」で発生する情報(空間情報と接触情報)を再構築させることによって生じる。情報の再構築が行為を創発する。また、ペルフェッティによれば、それは「物理的な差異を認知的な差異に変換する」ことに他ならない。
ただし、行為にとって身体(手)も世界(スイッチ)も情報ではない。なぜなら、暗闇で「ここにスイッチがある」という情報は、身体と世界の接点(中間)で生まれるからだ。それが物理的な差異を認知的な差異という意味に変換することだ。それが行為の学習の法則でもある。だから、すべての認知神経リハビリテーションは「身体と環境の相互作用」に基づいている。
このように記すと、認知神経リハビリテーションに取り組んでいるセラピストは、麻痺した手足に認知問題(空間問題と接触問題)を適用している臨床場面を想い浮かべるだろう。たとえば、上肢への空間問題(方向・距離)の訓練がある(図1)。この訓練は上肢の空間性の学習、正中線の認識、到達運動(リーチング)には重要である。しかし、この訓練では「ここにスイッチがある」という意識経験はできない。確かに、上肢の空間問題(方向・距離)では、「手の空間的な位置を触覚がガイド(誘導)している」が、たとえば机の上の平面を使う訓練の場合、手がどこに位置していても触覚は同じである。その触覚は上肢の運動の方向をガイドしても、「ここにスイッチがある」ということは教えない。暗闇で壁に手を接触させながら、いくら上肢の運動の方向を変えても、壁の接触感ばかり感じて、スイッチの接触感を感じなければ、「ここにスイッチがある」ことを知ることはできない。つまり、平面上の各位置の触覚は同じで、接触感の差異が得られないということである。

図1 上肢の空間問題(方向・距離):
この訓練は上肢の空間性の学習、正中線の認識、到達運動(リーチング)にはとても重要である。ただし、この訓練では「ここにスイッチがある」という意識経験はできない。
写真はサントルソ認知神経リハビリテーションの訓練場面である。
繰り返し強調するが、「ここにスイッチがあることを知ること」が重要である。その「私の手とスイッチの関係」とは、上肢の運動覚(空間情報)と手の触覚(接触情報)の関係である。それは上肢の運動覚の差異と手の触覚の差異が一点で出会うスイッチの場所という意味での情報(差異)なのだ。それが「情報とは差異によってつくられる差異」であり、厳密には「2つの差異でつくられる1つの差異」だと解釈すべきだろう。
上肢の運動の方向や距離がわかっても、手の触覚に変化がなければ、「ここにスイッチがある」という情報は発生しないということだ。そのための訓練での対策としては、平面上の各場所に、表面素材の差異を貼り付けることである。つまり、机の上の平面上に複数の表面素材を貼り付けて、触覚のバリエーションを配置しておく。そして、仮にスイッチに相当するのは唯一「チクチクする表面素材」だと決めておく。他の表面素材の接触感はスイッチではない。患者は閉眼し、セラピストによって上肢の運動の方向と距離はさまざまに動かされるが、その「チクチクする触覚」に出会った瞬間が、「ここにスイッチがある(汝自身を知る)」ことを意味する。これは上肢のタブレットや下肢の床面や傾斜板を使う空間問題でも考慮しておくべきである。また、最近の脳科学には「ラバー・ハンド」の研究が多く、身体所有感が論議されているが、ラバー・ハンドは「ここにスイッチがある」とは知覚しないだろう。
ベイトソンの「汝自身を知れ」とは、身体を知ることでも、世界を知ることでもない。それはペルフェッティが強調する身体と環境の関係(情報)を構築することである。「身体と環境の相互作用(手とスイッチの相互作用)」という物理的な情報から、「ここにあったのか」という認知的な情報が構築され、「電燈をつける」という行為が生まれる。
「ここにスイッチがある」という情報の「ここ」とは、内部(運動覚)と外部(触覚)が出会う場所のことである。また、音楽を奏でるギタリストやピアニストにとっての「ここ」とは、内部(運動覚・触覚)と外部(聴覚)が出会う場所のことであろう。触覚は「二重感覚」であり、行為によって内部にも外部にも意識の志向性を向けることができる。
人間は、身体と世界の相互作用に複数の意味を与えながら生きている。そして、「意味の宇宙」で「汝自身を知る」ことになる。
文献
- 1) グレゴリー・ベイトソン(佐藤良明訳):精神と自然:生きた世界の認識論.岩波文庫,2022.
| ←No.133へ | No.135へ→ |