
Home > 会長からのメッセージ目次 > メッセージNo.68
| ←No.67へ | No.69へ→ |
メッセージNo.68 フッサールの「間主観性の現象学」、「大丈夫、死ぬには及ばない」、「ヴィゴツキーの思想世界」
最近読んだ本を3冊紹介したい。いずれも認知神経リハビリテーションを理解し、その可能性に期待してくれている著者たちの本である。
・・・・・・・・・
1.「間主観性の現象学Ⅲ・山口一郎監訳・ちくま学芸文庫」
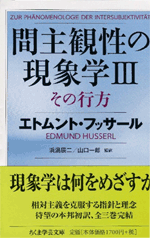 フッサールの「間主観性の現象学Ⅲ、−その行方」は、東洋大学教授の山口一郎先生の監訳本である。「間主観性の現象学Ⅰ、−その方法」と「間主観性の現象学Ⅱ、−その展開」に続く、三部作の完結編である。
フッサールの「間主観性の現象学Ⅲ、−その行方」は、東洋大学教授の山口一郎先生の監訳本である。「間主観性の現象学Ⅰ、−その方法」と「間主観性の現象学Ⅱ、−その展開」に続く、三部作の完結編である。
「間主観性」とは、「人と人の間(あいだ)の関係性」を意味する。特に、この第Ⅲ部では「自我」が記述されている。つまり、自我(私)は「間主観性」の産物としてある。それはフッサールの「現象学」における重要なキーワードでもある。
フッサールの現象学は超難解で、いくら読んでも全貌は理解できないが、認知神経リハビリテーションに取り組んでいるセラピストなら一度挑戦してみる価値がある。なぜなら、不意に理解できる文章と出会うからである。
たとえば、「知覚の類似性による合致は別のことをともなっている。私が身体をもってそこにいるかのように、しかも変容した身体物体とともにそこにいるかのように、という”表象”が一緒に呼び起されるのである,p63」という記述がある。
この記述から「ミラー・ニューロン」、「頭頂葉連合野(角回)」、「身体イメージ」、「異種感覚情報変換」、「多感覚統合」というキーワードが想い浮かぶはずだ。そして、脳卒中後の失行症(apraxia)や発達障害児の運動統合障害(dyspraxia)の治療に、「知覚の類似性による合致」が必要であることを再確認するだろう。
失行症や発達障害では「視覚、聴覚、体性感覚の知覚レベルでの合致」が障害されている。それは知覚情報の不一致であり、頭頂葉連合野(角回)における感覚情報の解読障害を意味する。それには同種感覚情報変換(視覚間、体性感覚間)と異種感覚情報変換(視覚と体性感覚間)とがある。
たとえば、見たもの(視覚)と触れたもの(触覚、圧覚、運動覚、重量覚)が一致しない。それによって自己や他者の身体イメージを想起することが困難となり、他者の身体の動きを見ても、自分の身体の動きとして脳内でシミュレーションできない。この問題の本質は知覚の類似性の合致の障害(多感覚統合不全)に伴う身体イメージの変容であり、それが「間主観性」や「自我の形成」を阻害する。
こんな風にフッサールの現象学を読むと、哲学と認知神経リハビリテーションの臨床をつなぐことができる。
おそらく、「間主観性の現象学」を翻訳する時、山口先生の頭の中ではフッサールの声が鳴り響いていたはずだ。その声は死んだ人間の生きている声である。人間には死んだ人間の声が聞こえる。「間主観性」は過去−現在−未来の意識をつないでいる。 フッサールの「間主観性の現象学」は、人間の意識の謎をめぐる探求の「金字塔」のような本として、長く読み継がれる一冊となるだろう。
2.「大丈夫、死ぬには及ばない・稲垣諭著・学芸みらい社」
 「大丈夫、死ぬには及ばない −今、大学生に何が起きているか」は、「リハビリテーションの哲学あるいは哲学のリハビリテーション(春風社)」を書いた自治医科大学教授の稲垣諭先生の本である。
「大丈夫、死ぬには及ばない −今、大学生に何が起きているか」は、「リハビリテーションの哲学あるいは哲学のリハビリテーション(春風社)」を書いた自治医科大学教授の稲垣諭先生の本である。
刺激的なタイトルは荒川修作の言葉だ。大学生の数奇な日常が綴られている。「自傷」、「拒食」、「離人」、「傾倒」、「幻視」、「強迫観念」など、若者たちの「心身の事故」のような体験がリアルに語られている。そこには精神だけでなく、身体の違和感のようなものがうごめいているかのようだ。違和感のある自我として生きることは辛いが、若者たちは懸命に日々を生きている。
この本を読みながら、「認知を生きる」という言葉が浮かんだ。認知神経リハビリテーションでは患者の身体についての「一人称言語記述」を重視する。まるで、それと重なり合うかのように、教師の学生への「心のケア」が綴られている。現象学的な方法論はリハビリテーションの臨床でも、教育現場でも重要だ。だが、教師も「心身の事故に遭遇してしまった学生たち」も苦悩している。そこからの脱出には「語り合う」ことが不可欠なのだろう。
そういえば、最近、精神科領域で「認知行動療法」や「オープン・ダイアログ」が注目されている。そこには自我の「物語(ナラティブ)」がある。違和感のある自我は物語の中に沈殿してうごめいているのだろう。それが他者の介入により治療できるとは限らないが、そのままにしておけばよいわけではない。語り合うことで、語っている本人が変化するのかも知れない。もし、そうであれば、「対話」は脳の可塑性に働きかける強力な手段となる。
「間主観性」の深度、つまり教師と学生との関係性の深度について考えた。臨床でのセラピストと患者の関係性の深度についても考えた。そして、「自分自身の深度はどうだ」という問いが脳裡をよぎった。「学生に語る」のではなく、「学生と語る」こと、「患者に語る」のではなく、「患者と語る」ことが重要なのである。
今、「心身の事故」に苦悩している若者が増えている。それはセラピストの大学や専門学校の教育現場でも無視できない状況になっている。彼らは僕らの近くにいて沈黙している。そんな時、この本を読んでいれば、教師や友人はその学生に声をかけることができるだろう。
本書は、「臨床哲学(現象学の臨床)」という学問領域をつくろうとする潮流に貢献する一冊である。その意味で認知神経リハビリテーションと底流を共有していると思う。
3.「ヴィゴツキーの思想世界・佐藤公治著・新曜社」
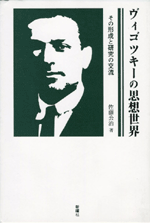 「ヴィゴツキーの思想世界−その形成と研究の交流」は、北海道大学教授の佐藤公治先生が退官と同時に出版した本である。
「ヴィゴツキーの思想世界−その形成と研究の交流」は、北海道大学教授の佐藤公治先生が退官と同時に出版した本である。
本書を読みながら、「研究者の魂」に触れたような気がした。そして、本のタイプは違うのだが、何故か「私の哲学、オートポイエーシス入門・河本英夫著・角川書店」や「フラグメンテ・合田正人著・法政大学出版」を読んだ時と同じ印象をもった。なぜなら、「学術的には語ることが困難な、別の何か大切なことが語られている」点では共通しているように思えるからである。そこに僕は不意に「研究者の魂」を感じたのではないだろうか。
「研究者の魂」とは、自己の興味、それも抜き差しならない興味である。研究者は何か、自分の知が求める何かに突き動かされて研究する。
だが、通常、研究者は主題について書く。巷には知をまき散らす本や、単なる説明に終わる本が幾多もある。あるいは、自分が研究した知見をまとめる本もある。おそらく、そうした研究者たちは自分が何を求めていたかを知っている。しかし、なぜ、自分がそれを求めていたのかは、個人的(私秘的)なことであり、自我の問題であり、一般的には学問の対象にはならない。
それにもかかわらず、そうした自己の興味、それも抜き差しならない興味について、人生をかけて探求するのが僕の思う「研究者の魂」の定義である。研究者の魂は、時に、そんな本を書かせる。それは単なる学術の嗜好や情熱の発露ではなく、「知の発露」のようなもので、個人的な香りがして僕は好きだ。
既に、「心理学のモーツァルト」と呼ばれるヴィゴツキーの著書は、すべて翻訳されている。彼の発達心理学はピアジェやブルーナーとともに今日でも生きている。また、神経心理学者のルリアに与えた影響も大きい。「未完のヴィゴツキー理論・神谷栄司著・三学出版」を読めば明らかなように、ヴィゴツキーの学術研究はかなり進んでいる。
しかし、ヴィゴツキー研究に一生を捧げたであろう佐藤先生は、ヴイゴツキーの自我に焦点を当てようと試みたように思う。つまり、「なぜ、ヴィゴツキーという人間の知が生まれたのか?」、あるいは「なぜ、自分はヴィゴツキーという人間の知に興味をもって生きたのか?」という問いに変えて、本書を書き上げたのではないだろうか。
それは「ヴイゴツキーが人間精神についてどのような思想を持っていたのか、そして彼の人間についての思想がどのような形で形成されていったのかを明らかしていく」という冒頭(はじめに)の言葉として簡素に記されているが、この一点が「研究者の魂」に由来するのである。
本書には、ヴィゴツキーの研究と生涯、ヴィゴツキーと芸術家(ロシア・フォルマリズム)、文学者(ハムレット)、映画監督(エイゼンシュテイン)、言語学者(言語論)、心理学者(ゲシュタルト心理学)との交流が詳細に記されている。ロシアの、ある時代の、友人との交流がヴィゴツキーという人間を発達させた。つまり、子どもの発達を長年研究してきた佐藤先生は、退官前に「ヴィゴツキーの発達」をテーマに選んだのである。
個人的には、ロシアの映画監督のエイゼンシュテインとの交流が興味深かった。いわゆる「モンタージュ理論(montage,映画に特異的な用語で、視点の異なる複数のカットを組み合わせて用いる技法のこと)」である。エイゼンシュテインは、このモンタージュ理論を確立した人物で、最も有名な作品は「戦艦ポチョムキン(1925)」である。
この重要性についてはドゥルーズが「シネマ・運動イメージ(法政大学出版)」で述べているように、「映像の運動的側面は内的なイメージと意味生成の可能性」を持っている。「モンタージュは、映像の各ショットが有機的に結びつき、衝突し、また反発し合いながら全体として一つの思想を描いていく」。「映画によって与えられる運動イメージは最終的には個々の運動イメージ同士を結びつけ、統合していくことで時間というトータルな人間の生の本質を作っていく,p145」
これは人間の行為(人間の意図ある身体運動)においても同様である点を忘れてはならないだろう。セラピストが患者の行為を観察する時も、共時的(ある一瞬の姿勢の空間性)かつ通時的(時間的に連続する姿勢の運動シィークエンス)に各動作の特徴や異常をモンタージュしながら観察しなければならない。セラピストの動作分析には視点の変換が不可欠なのである。
ここで僕はペルフェッティの言葉を思い出す。ペルフェッティには愛する一人娘がいるのだが、ある時「娘の結婚相手はエイゼンシュタインのモンターシュの意味を語る若者でなければならない」と言ったらしい。そのためか一人娘はまだ独身らしい。
また、認知神経リハビリテーションを勉強しているセラピストは「片麻痺(痙性)の特異的病理」という言葉を知っているはずだ。痙性は伸張反射の異常、放散反応、原始的運動スキーマ、運動単位の動員異常の4つの特異的病理に区別される。そして、この「特異的」という言葉はエイゼンシュタインのモンターシュ理論からの引用である。なぜなら、映画はモンタージュすることによって時空間を超えることができるが、それは映画に「特異的」だからである。痙性も4つの特異的な視点から観察されなければならない。その異常の組み合わせが片麻痺患者の行為や動作として表出される。
さらに、サントルソ認知神経リハビリテーション・センターの庭には「ヴィゴツキー広場」がある。ピサのプッチーニ先生とブレギー先生の小児クリニックは「ヴィゴツキー・認知神経リハビリテーション・センター」と名付けられている。
そんなエピソードを思い出しながら、この本を読んだ。ヴィゴツキーへの愛情に溢れた素晴らしい一冊である。
・・・・・・・・・
この3冊は「哲学」と「精神医学」と「心理学」の本である。3冊に共通するのは「自我の形成」である。他者と共に生きる人間の自我、心身を病んだ若者の自我、ヴィゴツキーの自我の形成である。
強調しておきたいのは、他にもリハビリテーションを一歩進めるために参考になる本が無数にあることだ。若いセラピストは携帯の画面ばかり見ずに、あるいは医学文献ばかり読まずに、若いうちに大量にさまざまな領域の本を乱読すべきである。そうやって自我を形成していってほしい。
ほら、この3冊のうち、どれを読もうとするか、それが自我だ。結局、読まないと決めるのも自我だ。そうやって自我は、日々新たに形成されてゆく。人間は自我という世界に複数の意味を与えながら生きてゆく。
また、自我を形成するための本は、リハビリテーションとは直接関係のない本棚の隅に置かれている本がいい。人間は偶然を生きる。そんな普段は決して読まない本と偶然出会い、その内容とリハビリテーションをつなげることから何かが生まれる。その”何か”がセラピストの臨床を変えると信じている。きっと、宝物は遠く離れた所に眠っている。
| ←No.67へ | No.69へ→ |
