
Home > 会長からのメッセージ目次 > メッセージNo.104
| ←No.103へ | No.105へ→ |
メッセージNo.104 微細脳損傷
1947年にStrauss(シュトラウス)は「脳損傷児(brain-injured child)」という新たな疾患(症候群)の概念を提唱した。この概念は従来の診断的範疇に合致しない症状の組み合わせを含んでいた。彼は脳損傷児の7つの症状を挙げている。
1.多動
患児はじっと坐っていることが出来ず、いつも動いている。ごくわずかな時間しか一つのことに止まらないで次から次へとその活動が移ってゆく。常に何かを指でさわったり、軽くなでたり、口に入れたりする。言葉の面でも、運動機能の亢進にはしばしば多弁と、まとまりのない言葉の流れが伴っている。
2.衝動性
患児は時々「ジェット推進」と形容されるような状態になり、衝動と実行に移すことが直結される。
3.注意集中時間の短さと注意の散漫
患児はどんな外部の音や視覚刺激に対してでも注意がすぐそちらに移る。教室でも友達のくしゃみ、廊下の足音、ドアが開くことなどで簡単にそちらに気がそれる。一つのことに時間を充分費やして集中することが出来ないので、何事もやりとげることが出来ず、従って持続的に目標に向かって仕事を続けることは不可能である。
4.協調運動の拙さ
一般的な協調運動、または細かい運動を遂行してゆく際の協調運動は、常に不器用でぎこちない。
5.学習困難
これは一方では異常に述べて来た特徴に基づき、他方、患児の多くが抽象的思考の不得意なことに基づく。
6.情緒不安定
多くの患児に、調子の良い日と悪い日、あるいは一日の内でも朝は良いが午後は調子が悪い(逆の場合もある)といった変動がある。欲求不満に耐える閾値の低さによってその結果、怒りの爆発と、その後に生ずる純粋ではあるが余り長くは続かない悔恨があらわれやすい。同じ子供が少し時間がたつと、非常に気持ちの優しい天使のような子になり得る。
7.自己概念の乏しさ
患児は常にしかも不安をもちながら、自分自身について困惑している。反省の機会を与えると、一部の患児はこういった言葉を口にする。ある子は涙ながらにこう言った。「やることなすことでまともに行ったものなんてないんです」と。また他の子は「僕なんかゴミ捨てに捨てちまえばいいんだ」と言っている。彼らの大部分が、自分は「駄目だ」と思っている。学業成績のあがらないことが彼らを自分は「阿呆」だと思い込ませている。落ち着きのなさは「どうにもならないこと」なのだと絶望的に肯定してしまっている。
このStraussが挙げた7つの症状は、脳損傷児の「問題行動」の特徴を的確に観察したものであり、この症候群が複数の症状(要素)の集合体であることを浮彫りにしている。ただし、Clemensが指摘しているように実際の症状の出現状況は一人一人異なる。
ある子がこれらの領域のすべて、あるいは多くの症状を持っているとは限らない。子供によってそれぞれ症状のクラスターは違っている。自分の欠損や偏りを補う機能の形や優劣はその子供の持つ知的なレベルや基盤にある気質傾向によって決定される.
また、当時、脳損傷児の治療は確立されていなかったが、Straussの業績を記した『カナー児童精神医学』には、当時の脳損傷児の治療についての基本的な考え方が次のように記載されている。
治療は、この症候群について、両親に解り易く説明することから始まる。親は多くは、子供の問題行動の一義的原因として自分自身を責めているし、他からも罪意識を感じるように仕向けられてきている。しかし、このようにして免罪符を受けとった両親は、患児に対して穏やかではあるが、しっかりした態度で外的なコントロールを加える必要があるという助言により上手に協力していくことができるようになる。
Straussの脳損傷児の提唱と観察は先駆的かつ貴重なものであった。しかしながら、脳損傷は証明できなかった。
その後、1957年にEisenbergが「微細脳損傷(minimal brain
damage,MBD)」、1962年にClemensが「微細脳機能障害(minimal brain
dysfunction,MBD」という用語を使用して広まってゆく。
そして、2013年に「注意欠如多動性障害(attention deficit hyperactivity
disorder,ADHD)」という診断名が確定されることになる。
その間の変遷についてはアメリカ精神医学会の「精神疾患の診断マニュアル(DSM)」の1968年の第2版(DSM-Ⅱ)、1980年の第3版(DSM-Ⅲ)、2013年の第5版(DSM-Ⅴ)の診断名が重要である。つまり、以下のように診断名が変遷した。
1947➡脳損傷児(brain-injured child)
1957➡微細脳損傷(minimal brain damage,MBD)
1962➡微細脳機能障害(minimal brain dysfunction,MBD)
1968➡小児期の多動性反応(hyperkinetic reaction of childhood, DSM-Ⅱ)
1980➡注意欠陥障害(attention deficit disorder, DSM-Ⅲ)
2013➡注意欠如多動性障害(attention deficit hyperactivity disorder,ADHD, DSM-Ⅴ)
2013➡ADHDは「神経発達障害(neurodevelopmental disorders)」に含まれる(DSM-Ⅴ)
つまり、Straussの「脳損傷児」、あるいは「微細脳損傷」は、現代では「注意欠如多動性障害(ADHD)」と呼ばれている。そして、いわゆる「発達障害」、あるいは「神経発達障害」の一つのタイプがADHDである。また、ADHDの診断では「多動(hyperactive)」、「不注意(inattentive)」、「衝動性(impulsive)」が重要視されるが、ADHDの症状には「学習障害(learning disorder」や「発達性協調運動障害(developmental coordination disorder,運動の不器用さ)」あるいは「運動統合障害(dyspraxia,子どもの失行症)」の症状も含まれている。
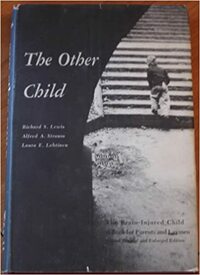
Strauss A:「The Other Child」,1951
Straussが観察した脳損傷児の7つの症状は、時代を越えた価値を有し続けていると思う。特に、「自己概念の乏しさ」への指摘は、子どもの発達を考える上で決して忘れてはならない核心であろう。子どもは「やることなすことでまともに行ったものなんてないんです」と言っている。リハビリテーションは「やることなすことがまともに行く」ためのものでなければならない。また、子どもは「僕なんかゴミ捨てに捨てちまえばいいんだ」と言っている。彼らの大部分が、自分は「駄目だ」と思っている。リハビリテーションによって自己否定の発達を自己肯定の発達へと変える必要がある。
なお、Straussには『The Other Child : The Brain Injured
Child(1951)』という本がある(図)。
彼がこのタイトルに込めた想いは深い。2020年、コロナ禍の中で発達障害児たちはどうしているだろうか。そのリハビリテーションに取り組んでいるセラピストにエールを送る。
文献
- 1)Strauss A,Lehtinen L : Psychopathology and education of the brain injured child. New York,Grune & Stratton,1947.
- 2) Kanner L : CHILD PSYCHIATRY. Charles Thomas Publisher,1972(黒丸正四朗・牧田清志訳:カナー児童精神医学.第2版,医学書院,1974).
- 3) Strauss A, Lewis R : The Other Child : The Brain Injured Child. New York,Grune & Stratton,1951.
| ←No.103へ | No.105へ→ |
