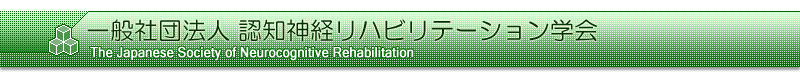Home > 会長からのメッセージ目次 > メッセージNo.131
| ←No.130へ | No.132へ→ |
メッセージNo.131 脳損傷と訓練の階層レベルは一致しているか?
[1]
19世紀末のパリ、20世紀の神経疾患の診断と治療に大きな影響を与えるサルペトリエール病院の「臨床神経学」が花開いていた。だが、意外かも知れないが、後世の神経疾患の診断と治療に多大な足跡を残したシャルコーやバビンスキーの業績をはじめとするサルペトリエール病院の臨床神経学は、リハビリテーション治療の進歩には必ずしも貢献していない。
その理由はサルペトリエール病院の「臨床神経学が医師の「診断」に特化していたからだろう。だが、ジャルコ―の『火曜日講義』を読むと、必ずしもそうでないことがわかる。
そこにはシャルコーと患者の「対話」が記載されている。シャルコーは患者にさまざまな質問をして、症状や病態について語らせている。また、その意識経験についても耳を傾けている。そこには患者の人生の物語、すなわち「ロマンチック・サイエンス」が数多く含まれている。
つまり、臨床神経学は医師の「診断」に特化しているとは言えるが、その診断に至るまでには「対話」という方法によって引き出された「患者の言葉」が含まれている。その点に誰かが気づいていれば、臨床神経学はリハビリテーション治療の進歩に貢献していた可能性もある。
[2]
ペルフェッティは約100年後の21世紀初頭に、医師の診断とリハビリテーション専門化(セラピスト)の観察の関係性について次のような憂慮を述べている2)。
外科医や内科医が診断にあたってとる思考は、リハビリテーション専門家が治療を通じて「どうすれば運動麻痺の回復の可能性を導けるのか」と考えながら行う観察時のそれとはかなり異なっている。また、どのような徴候に重要性をおくかもそれぞれの専門分野により変わってくる。臨床医にとっては、外科的もしくは内科的治療を行うために、損傷による病変の部位と特性とを理解したうえで診断を行うことが重要となる。一方、リハビリテーション専門家にとっては、それらは自分の本来の担当分野ではなく、観察から得られる諸データの一部に過ぎない。
ペルフェッティは何を問題提起しているのだろうか。それは診断のための観察と運動機能回復のための観察の違いという根本問題である。つまり、病的な運動麻痺の症状を詳細に観察して診断を下すことと、「どのようにすれば運動麻痺が回復するか?」と観察することは究極的な目的は同じでも内容は異なるのである。これは現在のリハビリテーションの臨床における回診、病棟でのカンファレンス、臨床研究、学生への教育内容、書籍や研究論文などを振り返れば明らかだろう。そこでは神経疾患の診断、症状、分析、予後などについては論議されるが、運動麻痺の回復についての観察や研究はなおざりにされている。医師による神経疾患の診断についての知識は画像による診断や各種検査データで細分化され、セラピストも日進月歩するそれらの知見を学んでいるが、最も重要な点が曖昧にされたまま長い歳月が経過してしまっている。これはリハビリテーション医学が独自の治療構築に向けた観察の視点を持たないことを反映していると言っても過言ではないだろう。セラピストは自らの治療に有益な観察の視点を持つ必要がある。つまり、ジャルコ―やバビンスキーのような医師の診断のための臨床神経診断学とは異なる、セラピストが運動麻痺を治療するための独自の臨床神経学的な「リハビリテーション観察学」が必要なのである。
そうした運動麻痺の回復に向けた臨床神経学はこれまで存在しなかったのだろうか。残念ながらそれが現在でも確立されていないことは確かだが、臨床神経学の歴史には医学とは異なる学問を応用して運動麻痺の新たな病態解釈に挑戦した医師がいた。それは19世紀後半に活躍したイギリスの神経内科医ジャクソンである。その革新的な思想は当時の一般的な運動麻痺の観察や解釈とは明らかに違っている。
[3]
ジャクソンは臨床神経学や精神医学の発展に貢献した人物であるが、本人は意図していなかったものの脳卒中片麻痺に代表される中枢神経疾患のリハビリテーション治療(運動療法)の理論面にも結果的に大きな影響を与えている。また、ペルフェッティは「私の尊敬するジャクソン」という表現で彼の思想に学んだことを表明している。
ジャクソンの思想は神経疾患の症状を厳密に分類して診断学を確立するという研究の方向性ではない。バビンスキーの業績のようにそれは医師にとっては非常に重要で価値ある研究の方向性であるにせよ、複雑多岐にわたる運動麻痺が発現する原因や理由を理論的に探求するという研究の方向性に最大の特徴がある。これがセラピストの治療に有益な知見をもたらす可能性がある。また、それは「あらゆる回復は病的状態からの学習であり、脳の認知過程を活性化して運動麻痺の回復を図る」という認知運動療法の考え方に妥当性を与えるはずである。
ジャクソンが世界的な名声を得たのは1884年に提出した『神経系の進化と解体(evolution and dissolution of centor nervous system)』によってである。これは後年「ジャクソニズム」と呼ばれ、臨床神経学や精神医学の発展に貢献した。神経系の進化と解体はスペンサーの進化論の影響下にある学説だが、神経系の進化は「中枢神経系の階層説(hierarchy of center nervous system)」を生み出し、神経系の解体は「陽性徴候と陰性徴候(positive sign and negative sign)」という概念を生み出した。いずれも神経疾患の病態や症状を理解する上で欠くことのできないものである。ジャクソンは随意運動の進化における中枢神経系の階層性を「最下位」、「中位」、「最高位」に段階づけた3)。
- 最下位は脊髄前角細胞と脳幹の脳神経核
- 中位は大脳皮質の運動野(前頭葉の中心前回:ブロードマンの4野)
- 最高位は大脳皮質の前頭葉連合野
最高位の前頭葉連合野(前頭葉の前頭前野:ブロードマンの9、10、11野および運動野前方の運動前野と補足運動野:第6野,運動性言語野:44野など)は神経系進化のクライマックスとしての「心の器官(organ of mind)」であり、意識の身体的基盤を構成するとされた。また、現代の脳科学は頭頂葉連合野や側頭葉連合野も心の器官であることを明らかにしている。
そして、注意すべきは最高位の「心の器官」を「最も少なく組織化されている」としている点である。最も複雑で、最も随意的な心の器官は最下位の脊髄・脳幹反射のように感覚刺激に対して自動的に組織化されているのではなく、逆に感覚刺激に対する反応に数多くの自由度がある点で最も組織化されていないと断定しているのである。ジャクソンは最高位中枢が「最高位運動中枢」であることの意味をジャクソンは次のように説明している4)。
身体的に見ると、人間は感覚―運動機構である。最高中枢−精神、あるいは意識の身体基盤は、次のような構造を持っている。すなわち、脊髄が身体の一部に限られた比較的小範囲の領域を直接代表するのに対して、最高中枢が無数の、種々様々な印象、身体のすべての部分の運動を間接的に表象(representation=再現)することを強調したい。最高中枢は「精神のためのものである」という返答が返ってくるだろう。それらが精神の身体的基盤であるという意味でそれを容認するとして、私はそれがまた「身体のためのもの」でもあることを主張したい。もし進化の理論が正しければ、すべての神経中枢は感覚−運動機構であるはずである。
フリッシュやフェリーの研究以来、私が中位運動中枢と呼んでいる脳中央部の運動野が運動を表象することが承認されている。脳のもっと前方の部分、私が「最高位運動中枢」と呼んでいる前頭葉が運動を再現しないのは何故かと問われるのは当然である。フェリーは脳の前方部分全体が運動性であると考え、「精神作業とは結局のところ、単に感覚性及び運動性の実体の主観的側面に他ならない」と述べている。これは私がこれまで長く主張してきたことであり、そう考える点では私と一致するが、中位及び最高位中枢を分ける点では私と一致しない。彼は私が最高位運動中枢と呼ぶところを単に眼と頭の運動を表象すると考え、私のように最高位運動中枢は身体のすべての部分を表象するとは考えていない。
最高中枢がすでに組織化ずみであるとすれば、新しい脳の組織化、新しい習得は不可能となる。最高位中枢が完全に自動的であるならば、「随意的」な心的操作というのは全くありえなくなる。すべてが組織化されていれば、新しい環境に正しく適応することは不可能になる。人間は特別な外部の状態に適応しなければならないが、新しい状態に対する新しい適応は起こり得ない。より完全に組織化されることとより自動的になることとは一つの事物の異なる側面に過ぎない。ありふれた例は字を書くことの学習であり、書くことは人間の思考や運動にかかわりをもつ。自動性にはさまざまな程度がある。最下位の最も組織化され、最も自動的な神経構造から神経の流れを受けて、自動化が始まる。最高中枢は最も複雑に進化しつつあるものであるが、しかしまた最も不完全に進化したものでもある。換言すれば、最高中枢は「もつれた終末」である。そこでは進化が最も活発に進行しているが、最低次の場合、たとえば呼吸中枢の場合では進化はおそらくほとんど完結している。
ジャクソンによって中枢神経系の階層説が構想された。彼は「たとえば、胸郭の同一の筋が、全く自動的な運動(呼吸)に、少し自動性の少ない運動(姿勢維持)に、ほとんど自動的ではない運動(発語)に関与する」と述べている。自動的で単純な運動をもたらす下等な最下位の中枢から、中位を経て、自動的でない複雑な運動をもたらす高等な最高位の中枢へと進化してゆくわけである。ジャクソンはこれを中枢神経疾患の観察から想定した。彼は痙攣発作がローランド溝周辺の中心前回を起源とする説を提唱していた。
また、もちろん1970年のフリッシュとヒッツィヒがイヌの前頭葉の中心前回に電気刺激を加えると手足の筋肉が収縮するという運動野の発見を知っていた。それにもかかわらず、この運動中枢である運動野が発見されたばかりの大脳機能局在論がこれから始まろうとする時代に彼が運動野を中位と位置づけたのは、随意運動が精神や言語による調節を受けていると考えたからである。その先見性と洞察力は彼が失語症の研究者であり、他の神経学者のような外部刺激による観察とは異なる観察力を有していたからこそ生まれたものだろう。後年、ジャクソンによる失語症の研究を神経心理学者のルリアが高く評価している。
いずれにせよ、中枢神経系の階層説は前頭葉が経験によって発達することで反射や反応を制御して随意運動が獲得されてゆくとする運動学習理論(motor learning theory)の曙だと言えるだろう。反射は随意運動ではない。随意運動は反射の集積や統合ではない。最高位の心の器官である前頭葉連合野が反射や反応を制御しているのである。ジャクソンは痙攣発作や運動麻痺の観察から発達の法則的な基本原理を見抜き、それを進化と呼んだのである。
[4]
そして、ここで紹介しておきたいのは、ペルフェッティが「疼痛のリハビリテーション」について言及した次の言葉である5)。
訓練のために選択された階層(ジャクソンの言う中枢神経系の階層)が、損傷が影響を及ぼしている階層ではなかったのではないか。訓練を行うことで実現されたのは一連の代償のみであり、それでは損傷以前の機能を完全に回復することはできない可能性がある(Perfetti,2006)
このペルフェッティの言葉は、セラピストの観察と訓練に対して、非常に重要な注意を喚起している。まず、セラピストは、臨床での観察から「損傷の階層レベル」を、治療計画においては「訓練の階層レベル」を明らかにしなければならない。
「疼痛」は、どの中枢神経系の階層レベルで生じているのだろうか(脳損傷の階層レベル)? また、疼痛に対する訓練は、どの中枢神経系の階層レベルに働きかけているのか(訓練の階層レベル)? この2つの整合性が重要だということである。
たとえば、疼痛は末梢の骨関節系の炎症に由来しているのだろうか? それとも第一次体性感覚野レベルの情報の不一致に由来しているのだろうか? あるいは、体性感覚と視覚の情報の不一致に由来しているのだろうか? さらには、体性感覚と言語理解の不一致に由来しているのだろうか? あるいは、神経障害性疼痛(神経因性疼痛)の階層レベルはどこなのか? 感覚レベルなのか、認知レベルなのか、情動レベルなのか?
一方、疼痛の治療としての温熱療法、運動療法における訓練としてのマッサージ、関節可動域訓練、筋伸張訓練、筋力増強訓練、体操療法、ミラー・セラピー、運動イメージ、行為イメージを利用した治療などは、どのような「訓練の階層レベル」なのか?
あるいは、複数のスポンジ(クッショク)の接触感の差異、接触部位の差異、接触の機能面(空間性)の差異、硬さの差異、あるいは心地よさ(情動)の差異などを体性感覚で識別させる認知神経リハビリテーションは、その患者に想起させる「知覚仮説(予測)」の難易度は、どのような「訓練の階層レベル」なのか? 運動軌道の方向、距離、形態の識別や、その運動軌道の体性感覚情報と視覚情報や言語情報との異種感覚情報変換の難易度は、どのような「訓練の階層レベル」なのか? さらに、過去の行為の想起を利用する「行為間比較」はどのような「訓練の階層レベル」なのか?
こうした「脳損傷の階層レベル(病態)」と「訓練の階層レベル(介入)」の整合性がなければ、疼痛の回復には決してつながらないだろう。
[5]
ジャクソンの中枢神経系の階層説は「反射➡反応➡随意運動➡行為」の進化を意味し、その反対は退行を意味していた。中枢神経疾患の病態の陽性徴候や陰性徴候の解釈としても有益であった。確かに、21世紀の脳科学が発達した現代において、「ジャクソニズム」は否定されてはいないが時代遅れの感がある。だが、セラピストが「損傷の階層レベル」と「訓練の階層レベル」の整合性の考慮を当然とするなら、あるいは病態への介入を通じて「どうすれば運動麻痺の回復の可能性を導けるのか」と考えるならば、ジャクソニズムは再び甦る。ジャクソニズムは亡霊ではない。ジャクソニズムはリハビリテーション医療の場で100年以上にわたって生き続けている。
ペルフェッティが問うているのは、患者の脳損傷(病態)とセラピストの訓練(介入)、その2つの階層レベルの整合性の根拠である。たとえば、骨関節系レベルの関節可動域訓練や筋力増強訓練などの運動療法では高次脳機能障害レベルの損傷の回復は明らかに困難だろう。脊髄レベルの反射を活性化しても、運動野レベルを活性化しても、行為レベルの病態を有する失行症は改善しないだろう。疼痛に対しても温熱療法が有効だとは限らない。片麻痺の痙性とADL訓練は明らかに階層レベルの整合性はないだろう。行為の脳内シミュレーションに異常な病態が生じていれば、運動イメージ・レベルの介入が必要だろう。脳の予測メカニズムにも階層性レベルがある。たとえば、触覚予測と他者の感情を予測することにはかなりの差異がある。
あるいは、運動療法の難易度(単純さと複雑さ)は運動学レベルであり、神経生理学レベルや神経心理学レベルには対応してはいないのかも知れない。また、認知神経リハビリテーションは脳の認知過程の病態に介入するとされているが、その訓練の階層レベルはどのように区分されているのか。認知問題による訓練の介入は基本的に知覚レベルに設定されている。
臨床で少なくともセラピストはジャクソンの中枢神経系の垂直な階層性だけでなく、大脳皮質の第一次体性感覚野から頭頂葉連合野に至る水平な階層性を考慮しておく必要があるだろう。手の触覚や運知覚の識別は頭頂葉の「第一次体性感覚レベル(area3・1・2)」、触覚の接触空間(機能面)はarea2、両側性の体性感覚の比較は第二次体性感覚野(area43)、物体の属性の触知覚はarea5.7レベル、他者模倣などの運動−視覚−言語間の異種感覚情報変換は頭頂葉連合野(area39)レベルなどである。また、随意運動の意図や運動プログラムも視覚、触覚、運動覚、運動イメージ、行為イメージ、情動、記憶、言語レベルによって階層レベルが異なる。どの頭頂葉−前頭葉運動関連領域(運動前野、補足運動野、帯状回、ブローカ野、海馬など)のループを活性化させようとしているかを考慮すべきである。
したがって、行為の感覚運動システムの回復のためには、損傷(病態)と訓練(介入)の階層レベルが一致しているかどうかの根拠についての論議が必要である。行為の感覚、知覚、認知と運動、動作、行為のレベルのカップリングについての論議が必要である。あるいは、回復や学習には損傷レベルよりもより高位のレベルの認知過程の活性化が有用かも知れない。
たとえば、セラピストが発達障害の子どもの上肢を他動運動しながら、その手指の机からの高さ(距離)の差異を問うのと、運動軌道として描かれた文字を問うのでは、明らかに情報処理レベルが異なる(図1)。


図1:発達障害の子どもに手指の机からの高さ(距離)の差異を問うのと、
他動運動で運動軌道として描かれた文字を問うのでは、脳の情報処理レベルが異なる
(写真は高橋昭彦:子どもの発達・学習を支援するリハビリテーション研究所より)
あるいは、体幹のコントロールが不良な片麻痺患者に上肢のリーチングと体幹の連携を求めたり、情動レベルで変容している半側空間無視患者に視覚探索を求めたり、視覚と視覚の同種情報変換が変容している失行患者に運動−視覚−言語間の異種感覚情報変換を求めることも、明らかに情報処理レベルが異なる。
さらに、ヴィゴツキーの発達の最近接領域を考慮すれば、意図的に損傷と訓練の階層レベルの差異をつくり、それに気づくように誘導することが回復や学習を促すのかも知れない。こうした論議はリハビリテーションの「臨床の知」を揺さぶる可能性を秘めている。
つまり、損傷(病態)と訓練(介入)の階層レベルが不一致な(合致していない)状態での訓練は、回復や学習にとって無意味な可能性があるし、逆にその差異が回復や学習にとって有意味な可能性もある。そして、こうした論議はシャルコーも、バビンスキーも、ジャクソンもしていない。こうした論議のルーツはルリアの神経心理学であろう6)。神経心理学では「神経」だけでなく「心(認知)」を考慮する。だから、ペルフェッティはルリアを「我々のマエストロ」と呼んでいる。
この小論を書きながら、サントルソ認知神経リハビリテーションセンターで研修していた時、ペルフェッティが失行症の症例検討会で「セラピストは臨床神経心理学者でなければならない!」と言っていたことを思い出した。
文献
- 1) 萬年甫:神経学の源流(1)−ババンスキーとともに−,東京大学出版,1968.
- 2) 宮本省三:リハビリテーション身体論(第8章:ジャクソンとリハビリテーション).青土社,2010
- 3) 山鳥重:ジャクソンの神経心理学.医学書院,2014.
- 4) 宮本省三:片麻痺−バビンスキーからペルフェッティへ.協同医書出版社,2014.
- 5) Perfetti C(小池美納・訳): 身体と痛みのはざまで.現代思想,vol.10,青土社.2010.
- 6) Luria A(鹿島晴雄・訳):神経心理学の基礎.創造出版; 第2版,2019.
| ←No.130へ | No.132へ→ |